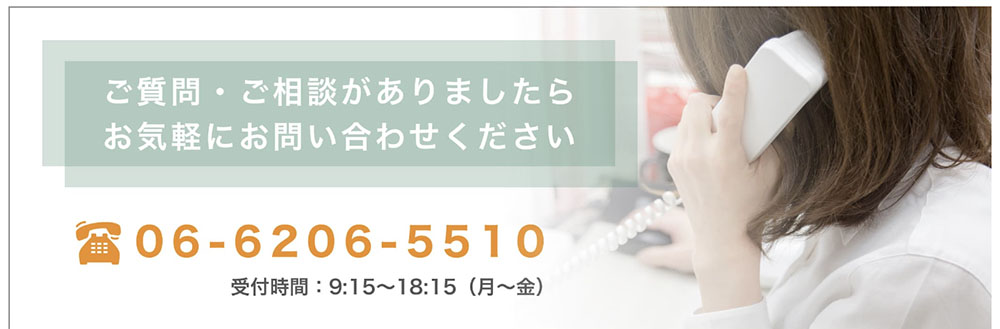医療法人化をご検討の先生へ
個人開業医として一定の経営規模に達した段階で、医療法人化を検討される先生が増えています。医療法人化には節税効果や事業承継のメリットがある一方、設立手続きや運営面での注意点も存在します。
税理士法人辻総合会計では、30年以上にわたる医療機関専門の経験を活かし、医療法人設立から設立後の運営サポートまで、トータルでお手伝いいたします。
医療法人化とは
医療法人とは、医療法に基づいて設立される法人で、病院・診療所・介護老人保健施設などを開設・運営することができます。個人診療所を医療法人化することで、法人として事業を継続し、税務面や事業承継面でのメリットを享受できます。
医療法人の種類
| 社団医療法人 | 最も一般的な形態。複数の社員(出資者)で構成され、理事会により運営されます。 |
|---|---|
| 財団医療法人 | 財産の寄付により設立される法人。社団より設立要件が厳しくなります。 |
| 持分あり医療法人 | 平成19年3月以前に設立された医療法人。現在は新規設立不可。 |
| 持分なし医療法人 | 平成19年4月以降に設立される医療法人。出資持分の概念がありません。 |
医療法人化のメリット
1. 節税効果
個人の累進課税(最高55%)に対し、法人税率は一定(約23〜34%)です。理事長報酬と法人所得に分散することで、トータルの税負担を軽減できます。
理事長報酬を給与として受け取ることで、給与所得控除を適用できます。また、家族を理事や職員として雇用し、所得を分散することも可能です。
退職金は税制上の優遇措置があり、将来のリタイア時に退職金として資金を受け取ることで、大きな節税効果が期待できます。
生命保険料、社宅家賃、退職金積立など、法人でしか経費にできない項目を活用できます。
2. 事業承継の円滑化
個人診療所の場合、廃止と新規開設の手続きが必要ですが、医療法人の場合は理事長の交代のみで承継が可能です。
法人として事業を継続できるため、患者さんやスタッフに安心感を与えられます。
3. 社会的信用の向上
医療法人化することで、金融機関からの融資や人材採用において、社会的信用が向上します。また、分院展開や介護施設の開設など、事業拡大の選択肢が広がります。
4. 資金調達の円滑化
法人として財務諸表を作成することで、金融機関からの信用が高まり、融資を受けやすくなります。設備投資や分院展開の際に有利です。
医療法人化の注意点
1. 設立・運営コストの発生
定款認証費用、登記費用、コンサルティング費用など、設立時に一定の費用が発生します。
社会保険料の負担増加、税理士・社労士への報酬、役員会や社員総会の開催費用など、個人診療所より運営コストが増加します。
2. 自由度の制約
医療法人の利益を出資者に配当することはできません。利益は法人内に留保するか、給与・退職金として支給します。
一定額以上の資産の処分には、都道府県知事への届出や認可が必要になります。
3. 行政手続きの複雑化
都道府県への決算届出、定款変更の認可申請など、個人診療所にはない行政手続きが発生します。
医療法人設立の要件
| 資産要件 | 設立時に一定の資産(現金・不動産・医療機器等)が必要です。都道府県により基準が異なります。 |
|---|---|
| 役員要件 | 理事3名以上、監事1名以上が必要です。理事のうち1名は医師・歯科医師でなければなりません。 |
| 定款・寄附行為 | 法人の基本規則となる定款(社団)または寄附行為(財団)を作成する必要があります。 |
| 事業計画 | 向こう2年間の事業計画書と収支予算書を作成し、都道府県の審査を受けます。 |
| 地域医療への貢献 | 公益性の高い法人として、地域医療への貢献が求められます。 |
医療法人設立までの流れ
現在の経営状況、将来の事業計画をヒアリングし、医療法人化のメリット・デメリットをシミュレーションします。医療法人化が本当に有利かどうかを、税務面・経営面から総合的に診断します。
都道府県の設立認可申請のスケジュールに合わせて、具体的な設立時期を決定します。多くの都道府県では年2回の申請受付となっています。
医療法人の基本規則となる定款を作成します。また、向こう2年間の事業計画書、収支予算書を作成し、実現可能性を精査します。
都道府県の担当部署に設立認可申請書を提出します。申請書類は膨大で、定款、事業計画書、役員の履歴書、資産目録、不動産の登記簿謄本など、多岐にわたります。
提出書類の審査が行われます。書類の不備や追加資料の提出を求められることもあります。審査期間は通常2〜3ヶ月程度です。
都道府県知事から設立認可書が交付されたら、2週間以内に法務局で設立登記を行います。登記完了により、医療法人が正式に成立します。
税務署、都道府県税事務所、市町村への法人設立届出を行います。また、保健所への診療所開設許可申請、厚生局への保険医療機関指定申請など、医療機関としての許認可手続きを行います。
個人診療所の資産(医療機器、内装、在庫等)を医療法人に譲渡します。譲渡価格の算定、譲渡契約書の作成を適切に行う必要があります。
個人診療所を廃止し、医療法人として診療を開始します。患者さんやスタッフへの説明、看板の付け替え、各種契約の名義変更などを行います。
当事務所のサポート内容
設立前サポート
| 医療法人化診断 | 現状分析に基づき、医療法人化のメリット・デメリットをシミュレーション。節税効果、社会保険料負担、運営コストを具体的に試算します。 |
|---|---|
| 設立スケジュール策定 | 都道府県の申請スケジュールに合わせた、最適な設立時期のご提案。 |
| 定款作成 | 医療法人の基本規則となる定款を、都道府県のガイドラインに沿って作成。 |
| 事業計画書作成 | 向こう2年間の事業計画書、収支予算書を作成。実現可能性の高い計画を策定します。 |
| 設立認可申請書類の作成 | 都道府県への申請書類一式を作成。複雑な書類作成を専門家がサポートします。 |
| 都道府県との折衝 | 都道府県担当者との事前相談、申請書類の説明に同行。スムーズな認可取得をサポートします。 |
設立後サポート
| 設立登記手続き | 司法書士と連携し、法務局への設立登記手続きをサポート。 |
|---|---|
| 各種届出代行 | 税務署、都道府県、市町村への法人設立届出を代行。 |
| 保険医療機関指定申請 | 厚生局への保険医療機関指定申請、保健所への開設許可申請をサポート。 |
| 資産移転のサポート | 個人診療所から医療法人への資産移転を、税務面から適切にサポート。譲渡価格の算定、譲渡契約書の作成を行います。 |
| 給与・社会保険手続き | 社会保険労務士と連携し、理事・職員の給与設定、社会保険加入手続きをサポート。 |
| 顧問税理士としての継続サポート | 医療法人設立後も、月次決算、税務申告、経営相談など、継続的にサポートします。 |
よくあるご質問
Q1. 医療法人化のタイミングはいつがいいですか?
一般的に、課税所得が1,500万円を超えてきたら医療法人化を検討する目安と言われています。ただし、将来の事業承継計画、分院展開の予定、社会保険料負担なども考慮する必要があるため、総合的な判断が必要です。
Q2. 設立にどのくらいの期間がかかりますか?
都道府県の申請スケジュールにもよりますが、準備開始から医療法人として診療開始まで、通常6ヶ月〜1年程度かかります。申請受付が年2回の都道府県が多いため、早めの準備が重要です。
Q3. 設立費用はどのくらいかかりますか?
登記費用、定款認証費用、コンサルティング費用などを含めて、総額で150万円〜300万円程度が目安です。ただし、都道府県や設立内容により変動します。
Q4. 個人診療所と医療法人、どちらが有利ですか?
所得水準、将来の事業計画、家族構成などにより異なります。当事務所では、具体的な数値シミュレーションを行い、お客様にとって最適な判断をサポートいたします。
Q5. 医療法人化した後、個人に戻すことはできますか?
制度上は可能ですが、手続きが非常に複雑で、税務上も不利になることが多いため、慎重な検討が必要です。医療法人化の判断は、長期的な視点で行うことをお勧めします。
医療法人設立支援の実績
税理士法人辻総合会計では、これまで100件以上の医療法人設立をサポートしてまいりました。医療機関専門の税理士事務所として、都道府県との折衝、複雑な書類作成、設立後の運営サポートまで、ワンストップでお手伝いいたします。
医療法人化をご検討の先生は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。