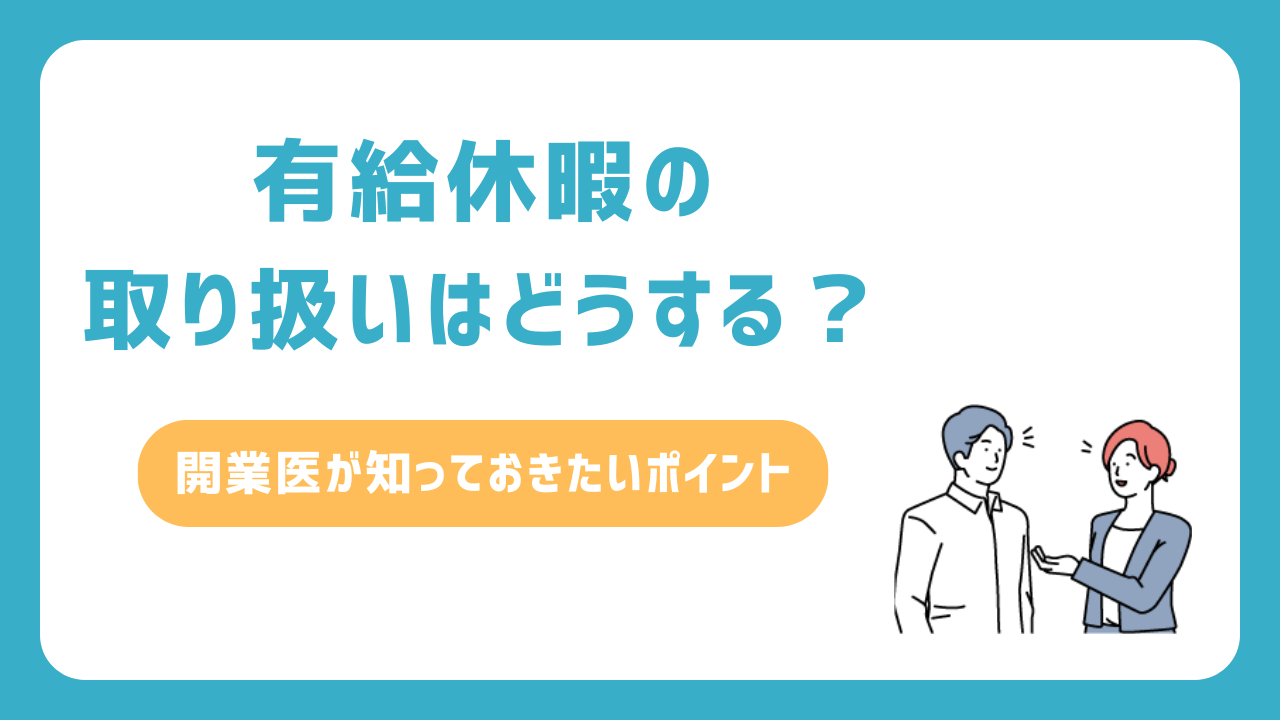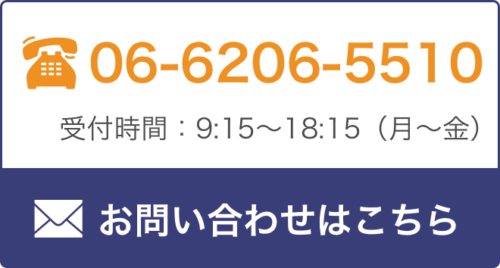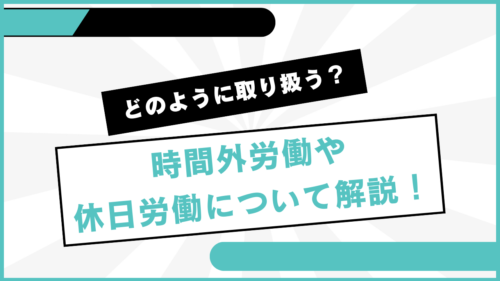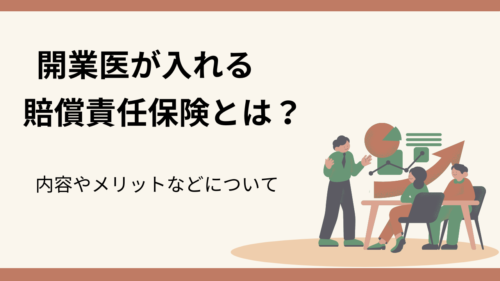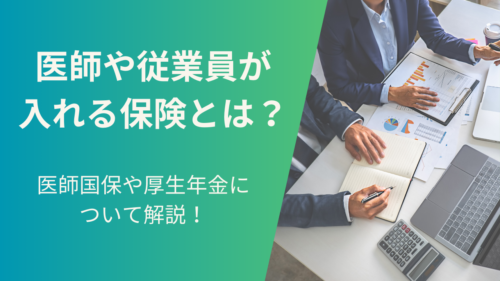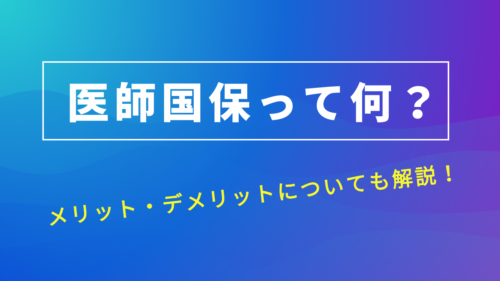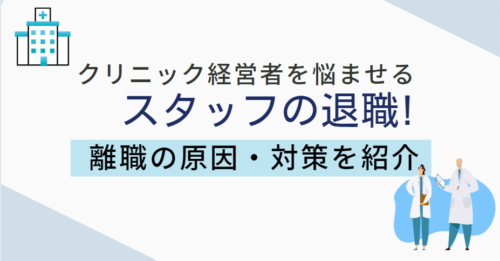「クリニックでの有給休暇の取り扱いはどうすればよい?」と悩む開業医も少なくないでしょう。
クリニックを経営する開業医の方は、従業員について様々なルールを考えなければいけません。その中の一つとして、有給休暇に関する事項があります。
有給休暇は従業員の働き方に影響するため、有給休暇に関する知識は、使用者である開業医の方にとって重要です。
この記事では、有給休暇の取り扱いについて、開業医の方が知っておきたいポイントを解説します。
\経営に関する相談は辻総合会計へ/
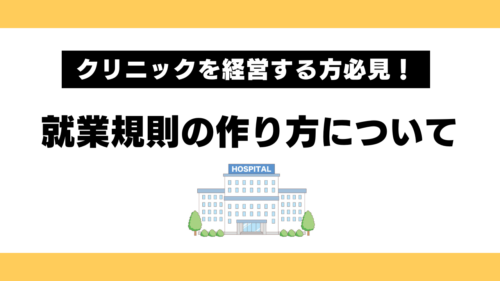
有給休暇についての基礎知識
はじめに、有給休暇に関する基礎知識を以下で解説します。
労働基準法によって定められた権利
有給休暇は労働基準法によって定められた権利であり、労働者が給与を受け取りながら休暇を取得できる制度です。
通常であれば従業員に対して休んだ日の分の給与は支払われません。しかし、有給休暇の制度を利用すれば、働いていない場合でも給与が支払われます。
有給休暇は従業員の健康を守り、生活を保障するものであるため、必ず取り扱わなければいけません。
有給休暇の発生要件と付与日数
【有給休暇の発生要件】
- 6ヵ月継続して雇われている
- 労働日の8割以上出勤
従業員が雇い入れの日から6ヵ月継続して雇われており、なおかつ全ての労働日の8割以上出勤している場合、使用者は原則として10日の有給休暇を与えなければいけません。
最初に有給休暇が与えられてから1年が経過し、その1年の間の8割以上出勤した場合は、11日間の有給休暇が与えます。1年経過するごとに上記の条件を満たせば、従業員が取得できる有給休暇の日数は増えていきます。
具体的な日数は、以下のとおりです。
| 雇い入れの日から経過した期間 | 与えられえる休暇の日数 |
| 6ヵ月 | 10日間 |
| 1年6ヵ月 | 11日間 |
| 2年6ヵ月 | 12日間 |
| 3年6ヵ月 | 14日間 |
パートタイマーの有給休暇
【対象】
週の所定労働時間が30時間未満、週の所定労働時間が4日以下、または年間の所定労働日数が216日以下
パートタイマーに対しても、有給休暇を与える必要があります。
パートタイマーの場合は、所定労働時間に比例して与えられる有給休暇の日数が異なります。
参照:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省
有給休暇に関するルール
有給休暇に関して確認しておきたいルールを、以下で紹介します。
従業員が請求する月日に与える
従業員が具体的に月日を指定した場合は、使用者は請求通りに有給休暇を与えることが原則です。
ただし、従業員の希望通りに有給休暇を与えることによって事業の運営に支障が出る場合は、他の月日に変更できます。使用者が持つこの権利を、時季変更権といいます。
有給休暇の請求権の時効は2年で、前年度に取得していなかった分は、翌年度に与えます。
参照:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
不利益な取り扱いをしてはいけない
使用者は有給休暇を取得した従業員に対して、不利益な取り扱いをしてはいけません。
不利益な取り扱いには、以下のようなものがあります。
- 解雇
- 給与を減らす降格
- 不利益な配置転換
- 契約更新の拒否
- 契約の更新回数の上限を引き下げ
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 昇進・昇格の人事考課において不当な評価 など
有給休暇の取得義務化について
法改正による有給休暇の取得義務化について、以下で解説します。
2019年4月~有給休暇に関するルール
有給休暇自体は昔からある制度ですが、法改正により有給休暇に関するルールが変更になりました。
2019年4月以降より、10日以上有給休暇が与えられた労働者に対して、使用者側が5日分の有給休暇を取得させる義務を負います。「10日以上有給休暇が与えられている」という条件を満たせば、正職員だけでなく、パートタイマーも対象となります。
改正前は、従業員から有給休暇の申請の希望があれば使用者が応じる、という形で問題ありませんでした。
しかし、改正後は使用者から従業員に有給休暇を取得するように働きかける義務が生じるようになりました。つまり、従業員側から希望が出ない場合でも、業務命令として取得させなければいけません。
有給休暇を取得させる義務を違反した場合
有給休暇を取得させる義務に違反すると、30万円以下の罰金が課されます。
また、従業員が希望する時季に応じなかった場合は、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が課されるので、十分な注意が必要です。
参照:「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
従業員の希望に沿えるようにする
使用者は従業員の意見を聞き、可能な限り従業員の希望に沿った取得時季になるように努めなければいけません。
ただし、従業員が既に5日の有給休暇を取得している場合は時季を指定する必要はなく、することもできません。
5日間の有給取得は「使用者側の時季の指定」「従業員側からの請求・取得」「計画年休」のいずれかの方法で取得すればよく、5日を超えた取得に法律が介入する余地はない、ということです。
【有給休暇の取り扱い】ケースごとの対応について
具体的な事例をもとに、有給休暇の取り扱いについて確認しましょう。
事後に有給休暇を申請された場合
病気などで休んだ日を、後日従業員から「有給として取り扱ってほしい」と相談されることはよくあります。
有給休暇は事前に申請するのが原則ですが、事後であっても労使間の同意があれば、有給休暇として取り扱うことが可能です。
しかし、一人の従業員に事後申請を認めてしまうと、他の従業員に対しても認めなければいけません。そうなった場合、クリニックの運営に支障が出る可能性もあります。
事後の有給休暇の申請についてのルールを就業規則に記載しましょう
事後の有給休暇の申請についてのルールを就業規則に記載すれば、トラブルを防ぐことにつながります。
書き方としては、以下の項目を記載することをおすすめします。
- 事後申請を認める理由
- 何日後までの申請を有給休暇と認めるか
- 事後申請の方法
上記の中で特に重要なのが、事後申請を認める理由です。
「体調急変などやむを得ない場合」「入院した場合」など、限定的に適用されることを明確にする必要があります。
有給休暇取得のルールが従業員に周知されていれば、人員不足などのリスク回避につながるでしょう。
退職時に有給休暇が残っている場合
従業員が有給休暇を使いきれず、残っている状態で退職日を迎えた場合、クリニック側が有給休暇を買い取ることも可能です。
本来、有給休暇の買い取りは原則として認められておらず、違法です。しかし、退職時に消化できなかった有給休暇に関しては、例外的に買い取ることが認められています。
使用者は、事前に従業員から残っている有給休暇の日数を聞いておきましょう。また、退職日までのスケジュールや、有給休暇を退職日までに消化する予定があるかなども確認するとよいです。
半日の有給休暇を申請された場合
従業員が半日の有給休暇を申請するケースは、クリニックではよくあります。
半日を0.5日とすることで、5日の有給休暇に含めることができます。
半日で有給休暇を取得した日に所定労働時間を超えて残業した場合、所定労働時間を含めて8時間を超えていなければ、残業とはならず、残業代を支払う義務は生じません。
まとめ
クリニックを経営する開業医の方にとって、有給休暇の取り扱いは重要です。
有給休暇は従業員に与えられた権利ですが、就業規則でルールをしっかりと定めることも大切です。
開業前に有給休暇に関する事項を確認したい、復習したいと考えている医師の方は、この記事をぜひ参考にしていただけたら幸いです。
クリニック・医院の開業や経営については「辻総合会計」へ
辻総合会計は開業医の医師たちが医業に集中できるように、労務や経営、税務に関するサポートを行います。
当事務所は、医療分野の開業や承継などのサポートをしてきた豊富な実績と知識がある事務所です。
クリニックをはじめとする医療分野の経営は、医業に強い税理士法人 辻総合会計にぜひお任せください。