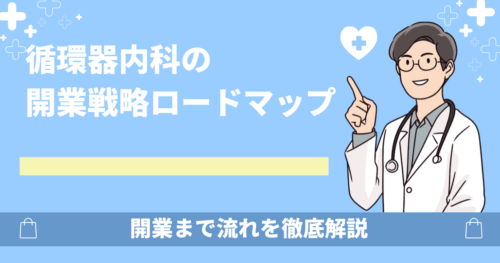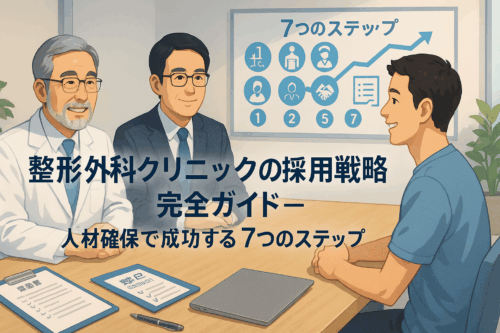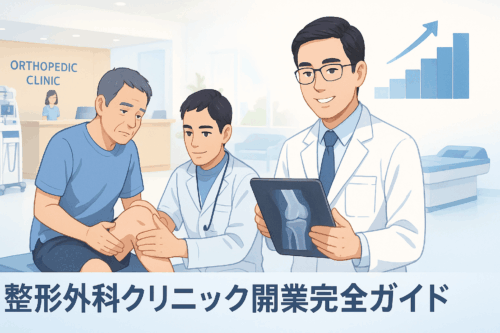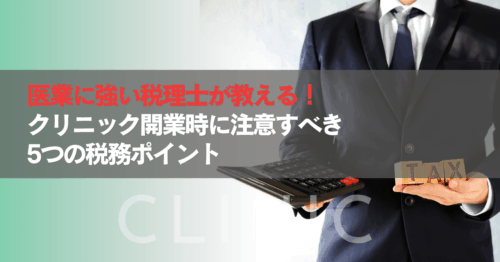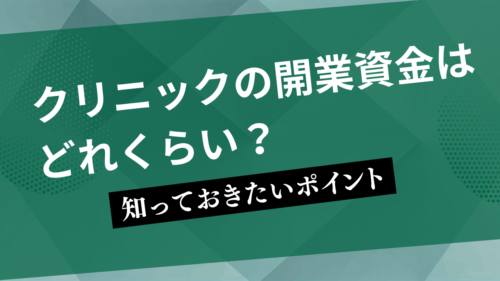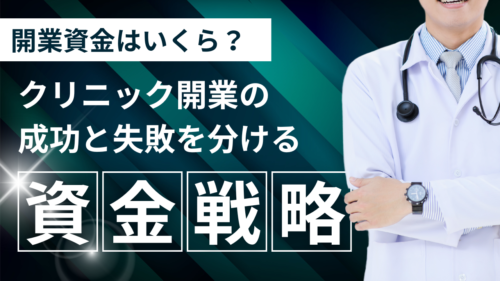少子高齢化により医療の需要が高まっている中、クリニックの開業を考えている人も少なくないでしょう。
クリニックを開業できるのは、医師だけではありません。条件がそろえば、医師免許がなくてもクリニックを開業できます。
この記事では医師以外がクリニックを開業する方法や、医師以外がクリニックを開業するメリット・デメリットについて解説します。
医師以外でもクリニックを開業できる?
医師以外でも、クリニックの開業は可能です。ただし、条件があります。
医療法7条により、医師・歯科医師以外が診療所を開く場合は都道府県知事の許可が必要です。(地域によっては、非医師様式が用意されています)
医師以外の方でクリニックを開業する際には、条件を満たし、専門家に相談しながら開業を行っていきましょう。
管理者は医師免許が必要
新規クリニックを開業するには、管理者が医師免許を保持していることが必須となります。患者に対して医療サービスを提供する上で、専門的な知識と技能が求められるためです。
クリニックによっては、「開設者」と「管理者」が異なる場合もあるでしょう。
管理者つまり院長は患者の診断や治療を行う責任があるため、医師としての資格がない場合、クリニックを運営することはできません。
条件により開設が可能
近年、医師以外でも条件を満たすことでクリニックを開業できるケースが増えています。
例えば、看護師や薬剤師など医療に関する資格を持つ専門職が、法人としてクリニックを設立することで開設できます。ただし、患者診療は医師が行う必要があり、必ず医師を雇用することが求められます。
医師以外でもできるクリニック開業方法
前述したように、医師以外でもクリニックの「開設者」になることは可能です。
医師以外がクリニックを開業する方法は、以下のとおりです。
- 一般社団法人の設立
- 医療法人の設立
- 医療法人のM&A
それぞれについて、解説します。
一般社団法人の設立
医師でなくても、一般社団法人を設立すればクリニックを開業することは可能です。
法人がクリニックを運営し、医師を雇用して診療を行う形になります。
ただし、実際の診療行為は必ず医師が行う必要があり、医療法や医師法に基づいた運営が求められます。
一般社団法人によるクリニック解説は可能だが、保健所の許可にハードルが高く、地域差も大きい
医療法人の設立
医師以外の人でも条件を満たせば医療法人を設立し、クリニックを開業することは可能です。
医療法人は、営利目的でなく公共性を重視した組織とされており、開設や運営には都道府県の認可が必要となります。
ただし、医療法人の理事には原則として医師が含まれている必要があり、実際の診療行為は医師が行います。
医師でない人が出資し、経営に関与する形も取れますが、医療法などの厳格なルールに従って運営する必要があります。
医療法人の理事長は、医師または歯科医師のみが就任できると法令で定められている
医療法人のM&A
医師でなくても、既存の医療法人をM&A(買収)することで、クリニックの経営をするすることは可能です。
買収後は医療法人の経営者として、施設運営や人材管理などに携わることができます。
ただし、医療法人の理事には医師が含まれている必要があり、診療行為は必ず医師が行います。
医師以外がクリニックを開業するメリット
医師以外の方がクリニックを経営することには、いくつかのメリットがあります。
具体的には以下のような点が挙げられます。
経営ノウハウの活用
医師ではなく経営の専門家やビジネスパーソンが経営を担うことで、効率的な運営や財務管理、集客戦略などに強みを発揮できます。
医師で経営のノウハウを十分に理解している人は多くはいないでしょう。
そのため、医師は診療をしながら経営を視野に入れ運営することは、効率的とはいえません。
リスクの分散
医師資格を持たない経営者が運営に携わることで、医療行為に関わる責任やリスクを分散できます。
経営者と医師の役割を分離することで、トラブル時の対応も明確になるでしょう。
事業多角化や拡大
医療だけでなく、関連分野や他のビジネスと連携したサービス展開を行いやすくなります。例えば、介護・福祉事業や不動産運営などです。
経営の柔軟性が向上し、事業の拡大が期待できるでしょう。
医師以外がクリニックを開業するデメリット
医師以外の経営者がクリニックを運営するには、医療に関する法令遵守や診療の質の確保、医師との連携をきちんと行う体制を整えなければ、法的リスクや信頼低下などのデメリットを伴うことが多いです。
ここでは、医師以外がクリニックを経営する場合のデメリットについて具体的に説明します。
医療の専門性と信頼性の低下
医師でない経営者は医療知識や診療の実務に不慣れなため、医療の質や安全性に関する判断や管理が難しくなる場合があります。
そのため、患者からの信頼や満足度が低下する恐れがあります。
法規制・コンプライアンスの理解不足
医療法や保険制度など医療に特有の法律や規制を理解し、適切に対応するために専門的な知識が必要です。
医師以外の経営者は専門的な法律を十分に把握していないことが多く、法令違反や行政指導を受けるリスクが高まる可能性があります。
医療行為の適正管理の難しさ
医療行為や診療内容の管理・監督において、医師の資格と経験が不可欠です。
医師以外の経営者がこれらの管理を担うのは難しく、診療の質を妥当に維持するための仕組み作りが課題となります。
業務範囲の制限と事業リスクの増大
医師資格がない経営者は、医療行為そのものを行えないため、医師の雇用や協力が必要になります。
また、経営上の意思決定と医療行為の責任の分離など、管理が複雑になりやすいです。
クリニック開業はまず税理士へ相談を!

クリニックの開業、そして成功をするには専門家による支援が重要です。
税理士、とくに医業に強い税理士であれば、リスクを最小限に抑え、資金調達のアドバイスや各種届出・手続きのサポートをしてもらえます。
医業に強い税理士へ相談しましょう
医師以外がクリニックを開業する場合、医療業界特有のルールや経営のポイントを理解しておくことが必要です。
そこで、医業に強い税理士に相談することで、法人設立の手続き、税務、資金計画、収支予測などを的確にサポートしてもらえます。
とくに医療法人やMS法人の運営は法的な制約が多いため、専門知識を持つ税理士の助言があることで、無駄なリスクを避け、安定したクリニック経営につながります。
開業事業計画書の作成を依頼できる
医師以外がクリニックを開業する際には、資金調達や行政手続きのために「開業事業計画書」の作成が必要です。
開業事業計画は、収支予測・運営方針・人員体制などをまとめたもので、銀行や自治体への提出にも使われます。
医業に詳しい税理士に相談すれば、実情に即した現実的な事業計画書を作成してもらえるため、資金調達や許認可の取得がスムーズになります。
資金調達計画のアドバイスを受けられる
医師以外がクリニックを開業する際には、多額の資金が必要になるため、しっかりとした資金調達計画が欠かせません。
税理士に相談すれば、自己資金の活用方法や金融機関からの融資、助成金・補助金の活用など、状況に応じた最適な資金調達方法をアドバイスしてもらえます。
とくに医業に詳しい税理士であれば、金融機関に信頼される事業計画書の作成もサポートしてくれるため、融資審査が通りやすくなり、安定したスタートを切ることが期待できるでしょう。
人事労務関係手続のサポートを受けられる
医師以外がクリニックを開業する際には、医師や看護師などのスタッフを雇うために、人事や労務に関する手続きが必要です。
税理士に相談すれば、給与計算や雇用契約、社会保険・労働保険の手続きなど、人事労務に関する業務を一括でサポートしてもらえます。
とくに医療業界はシフト制や資格管理など独自の労務管理が必要なため、経験豊富な税理士の支援を受けることで、法令遵守とスタッフの働きやすい職場環境づくりが両立でき、円滑な運営につながります。
集患・増収について相談できる
医師以外がクリニックを開業する際には、安定した経営のために「集患(患者を集めること)」や「増収」の対策が重要です。
税理士に相談することで、地域のニーズに合った診療科目の選定や価格設定、広告戦略、収支バランスの見直しなど、経営面からの具体的なアドバイスを受けられます。
また、過去の医療機関のデータをもとにした分析も可能なため、実践的で成果につながる提案を期待できます。